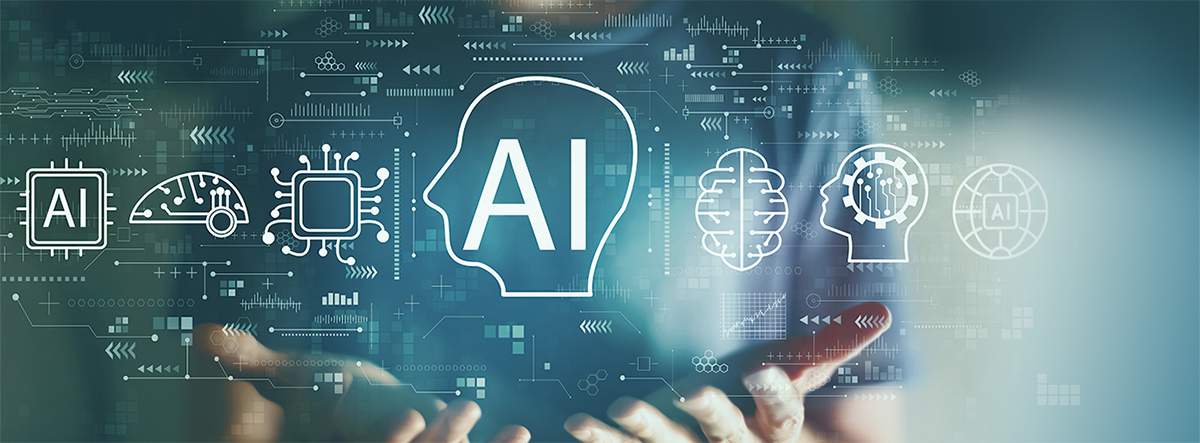MEMBER
-

SYSTEM ENGINEER2015年入社
-

SYSTEM ENGINEER2006年入社
AIを取り入れたソリューションで、
従来のICTでは実現できない高付加価値を提供。

「AIを活用してカタログ制作を効率化できないか」――そんな相談を持ち掛けてくれたのは、170万人近くの会員数を有する通販最大手のお客様。毎週、会員向けに「商品カタログ」を発行しているが、カタログ制作には企画(商品選定)・誌面割付・DTP(DeskTop Publishingの略。パソコンを用いて印刷物のデザイン及び印刷用データを制作すること)・校正・印刷といった全工程を行うのに半年近い期間を要していた。旬やトレンドを取り入れた商品を掲載するためにも、制作期間の短縮が急務という状況だ。富士フイルムBIジャパンは、かねてからこのお客様へ大規模デジタル印刷機などの印刷領域におけるサービスを提供しており、その実績から厚い信頼を得ていた。AI領域に関しては実績がなかったが、メーカー機能を持つ富士フイルムBIでは、AIを取り入れた新規サービスの提供に向けて、着々と準備が進んでいたタイミング。今回の相談は、富士フイルムBIジャパンが本格的にAI案件を獲得するための「好機」となったのだ。「富士フイルムBIジャパンと富士フイルムBIは日頃から情報共有をし、プロジェクトにおいてもタッグを組んで対応することがよくあります。今回も、技術面を支援する富士フイルムBIのSEと、お客様との接点を担う富士フイルムBIジャパンのフィールドSEの連携力を活かした案件です」とフィールドSEは当時のことを振り返る。
「本案件は10社競合。提案形態は各社によりばらつきがあり、中にはパッケージソフトウェアで提案した競合企業もあったようです。一方で、当社はAIを用いたソリューションの開発で豊富な実績をもつAIベンダーと協業し、要望に柔軟に対応できるよう、敢えて『スクラッチ開発』を提案しました」と、フィールドSE。「お客様の課題と真正面から向き合い、丁寧にヒアリングを重ねながらニーズに応えてきた実績から、今回の案件においても、お客様独自の業務ルールにAIを適用するにあたって、『現場業務に泥臭く入り込んで理解したうえで最適なソリューションを提供してくれる』と判断してくださったのだと思います」。
提案段階でヒアリングを進めていくに連れ、「ベテラン社員が担当していたカタログ制作の業務を、新入社員でも可能にする」「需要予測に基づいた商品選定や特価の判断を自動化する」「顧客の信頼を損なうようなミスを防ぐ」などのカタログ制作効率化以外のニーズも見えてきた。これらのニーズは従来のICTで対応することが難しく、AI技術を取り入れることで実現不可能だった要望にも応えることができるとフィールドSEは確信した。一方、富士フイルムBI のSEは、「AIへの理解促進」に向けた取り組みを進めていた。AIを取り入れたソリューションはお客様にとっても初めての試みとなるため、お客様の社内で勉強会を実施。役員から現場社員に向けてAIへの理解促進を行ってもらったほか、プロジェクトに対する認識の共通化を図った。こうして富士フイルムBIジャパンと富士フイルムBIの連携力が結実し、10社競合を勝ち抜いて正式にプロジェクトがスタートしたのは、2022年初頭のことだった。「大手SIerに勤務するSEの多くが大規模プロジェクトのメンバーから入ることが多いなか、富士フイルムBIのSEはお客様の課題に対して自分自身の裁量で自社・他社問わず技術を設計して提案し、お客様のビジネスに貢献することができるのが特徴であり、醍醐味だと思います。本案件に関しても、お客様の課題をSE自らヒアリングし、ベンダーを巻き込みながらAI技術を用いた提案を仕立てました。AIに特化した競合企業もいる中で、弊社を採用頂けたことをうれしく思いますし、非常にやりがいを感じます」。
新たな挑戦ゆえの困難を、富士フイルムBIとの連携で乗り越える。

プロジェクトが正式にスタートしたものの、その後は苦労の連続であった。第一に、AIを取り入れたソリューションの開発は、従来のシステム開発と大きく異なる。通常のシステム開発ではゴールを明確に定義した上で開発を進めていくが、AI開発では機械学習に必要なパラメーターを設定し、目標とする精度を設定する。そして、適宜パラメーターを追加して機械学習を繰り返し行いながら、目標精度に近づけていくアジャイル型の開発形態をとる。「何もかもが通常のシステム開発と異なるため、あらゆるシーンで試行錯誤の日々でした。例えば要件定義では、どの範囲をAIに担当させて、どの範囲を従来通り手作業で行うべきなのかを検討した上で、AIの精度指標を定義しなければなりません。すべてが手探りであり、それ故にスケジュールにおいてもゴールイメージが描きづらいという状況でした」とフィールドSE。
そのような中で助けられたのが富士フイルムBIとAIベンダーからのタイムリーで的確な助言だった。「プロジェクト全体を俯瞰した視点から、次に進めるべき一手を示唆してくれました。彼らの助けがなければ、これほどの精度で本案件を実現することは難しかったと感じます」。
AIの導入にあたって、現場の担当者からの反発もあったという。「従来の業務を大きく変え、AIの判断を信頼していただくようになるためには時間も必要です。現場の担当者一人ひとりと会話をし、業務利用のハードルを下げるのはお客様との接点を担う私の役割です」とフィールドSE。根気強く丁寧に説明を重ねていった結果、カタログ制作の担当者と信頼関係を構築でき、前向きにプロジェクトに協力いただけるまでになった。
AIとルールベースのハイブリッド処理で、担当者の思考を再現。

今回の案件において、最大のハードルとなったのが「掲載商品の選択」である。これまで、担当者が行っていた掲載商品の選択をAIが行うにあたって、「どこまで担当者の思考を再現できるか」が焦点となったのだ。「カタログに掲載する商品を選んでいる担当者は20~30名。彼ら一人ひとりがその都度、『会員のためにどの商品をお勧めすべきか』を判断しています。これをAIが担うということは、担当者の思考も考慮する必要があることになりますが、現在のAI技術では、担当者一人ひとりの人の感情や心理までも汲み取り、『暗黙知』を判断することはまず不可能でした」。
では、どのようにしてこのハードルを乗り越えていったのか。「担当者一人ひとりにヒアリングを行い、彼らの『暗黙知』を洗い出していきました。例えば同じ商品でも、重量や個数が違うものを掲載している場合。ある週にうなぎ一尾を掲載し、その翌週にうなぎ二尾を掲載していたとしたら、その意図を詳細にヒアリングしたのです。これには大変な労力がかかりましたが、その甲斐あって担当者ごとの明文化されていないルールを洗い出すことができました」。「AI」と、担当者特有の思考やルールを適用させた「ルールベース」の方法を組み合わせることで、お客様が求める商品選択を実現させていったのである。
このように、今回の案件を進めるにあたって、いくつもの高いハードルを乗り越える必要があった。ときにはAI特有の開発手法を受け入れてもらうことができず、お客様から「AIを導入する意味があるのか。本当にカタログの制作期間を短縮できるのか」と厳しい意見を頂戴したこともあったという。「AIの特性上、従来のシステム開発のように完全形を目指すことは難しく、目標となる精度を設定し、精度向上を目指していきます。当初は、この精度という概念を理解していただくのに苦労しました。そこで、定期的に報告会を実施し、現場の担当者や役員に向けて進捗状況を詳細に報告しました。また、AI開発では試験運用というかたちで開発途中のAIをお客様に評価していただき、フィードバックを生かして開発を行っていきます。つまり、評価と改修を行いながら、だんだんと精度を高めていくわけです。半年近く評価と改修を繰り返していった結果、お客様に満足いただけるだけの精度を実現することができました」。
部門を超えた連携により、
AIをより身近で汎用的な技術として活用する。

富士フイルムBIジャパンに対するお客様の評価は非常に高く、ハイブリッド処理による商品選択はもちろん、割付など他の業務のAI化についても評価いただいている。開発途中の段階に、すでに新たな相談も入った。「お客様からは『次はWEB発注システムにAIを導入したい』とのご相談をいただいています。以前、コロナ禍で一度に大量の注文が入り、欠品状態が続いたことがあったそうです。この案件を正式に受注することになったら、過去の受発注データから注文異常を検知し、在庫のコントロールや注文の一時差し止めなどの判断ができるAIソリューションを実現したいですね」と展望を語る。
AIを導入したソリューションの提供により、印刷の領域にとどまらないDXを実現することができた。提案できる技術の選択肢にAIが加わったことによって、さまざまな業種や分野に応用できる可能性が拓けたのである。とは言え、現段階ではまだAIを積極的に提案に取り入れるだけの知見を得たとは言い難いのも事実だ。「日本は米国などに比べて、AI活用はいまだ大きく遅れていると言われています。裏を返せば、国内のあらゆる業種においてポテンシャルが大きいということになる。今回の実績を試金石に、当社の研究開発力を活かして AIをより身近で汎用的な技術として活用できるよう、部門を超えた連携も進めていきたいです」。今回のプロジェクトを進める中でAIに関する知識の必要性を痛感し、自主的にG検定資格*を取得したというフィールドSEは笑顔でそう語る。AIという新たな領域に一歩踏み出した富士フイルムBIジャパンの挑戦は、まだ始まったばかりだ。
*一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施するAI・ディープラーニング活用のためのリテラシーを有しているかを認定する資格